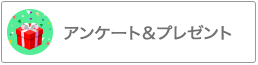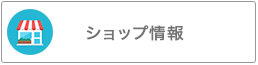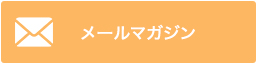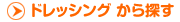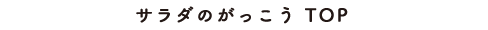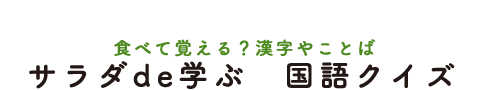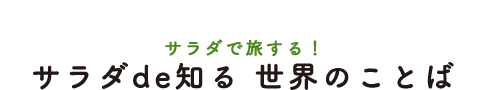日本史クイズ

数々の飢饉から、
人々を守ってきた豆ってなぁに?
初夏になると店頭に並ぶ、
緑色の大粒の豆といえば…
答えはイラストをクリック!
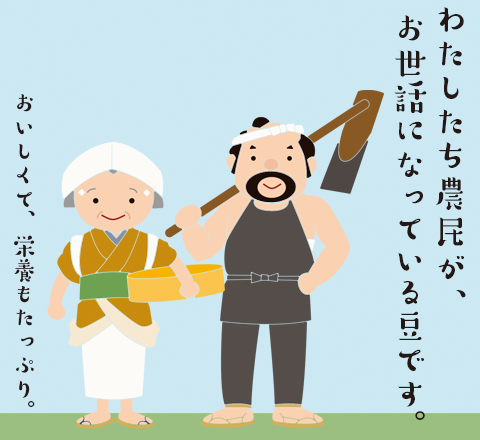
未熟なうちに食べる豆
答えは、そら豆。わかりましたか?ところで、皆さんはそら豆を鮮やかな緑色のうちに茹でたり、蒸して食べていますね?この「緑色」=「未熟なうちに食べられる」という、私たちにとって当たり前のことが、昔はとても大事なことだったんです!
そら豆が人々を救った理由とは?
江戸時代、元禄10年に刊行された『農業全集』(農学者・宮崎安貞著)によると、そら豆は「百穀に先立て熟し、青き時莢ながら、煮て菓子にもなり、又麦より先に、出来るゆへ、飢饉の年取分助となる物なり。」とあります。これは、「すべての穀物より先に熟して、青い時から食べられる。また麦より先に実るので、飢饉の時などに助けになる食物だ」ということです。
江戸時代の「すきま」家庭菜園
そら豆は、米や麦を育てた後の田畑の隙間(すきま)などで栽培していたそうです。これは、田の畦や土手などで収穫された作物は、年貢(課税)の対象にならなかったから。早く作れて、自分たちで食べることが出来るそら豆は、江戸時代の農民を厳しい年貢の取り立てや飢えから救っていたといえるのです。
そら豆は、蚕豆?空豆?
「そら豆」という呼び名に蚕豆という漢字をあてるのは、蚕(かいこ)が作る繭(まゆ)の形に似ているからといわれています。また、「空」の漢字を使うのは、天に向かって実がなるからと、宝永6年に刊行された『大和本草』(儒学者・貝原益軒著)に書かれています。
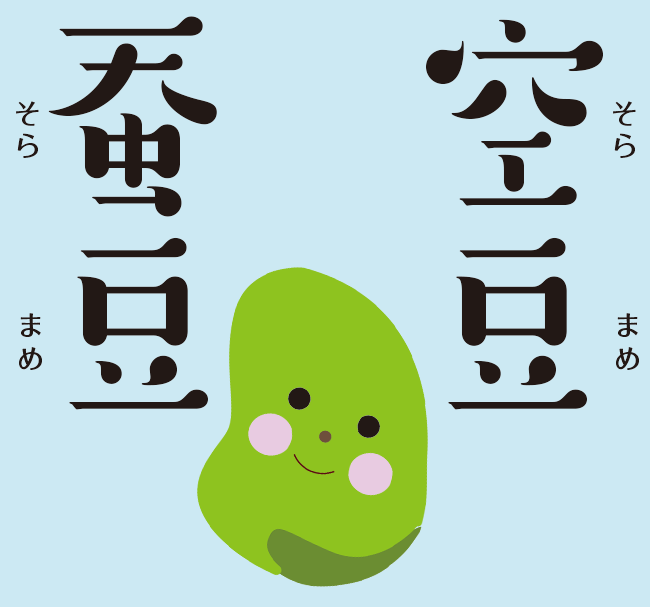
それでは世界史!そら豆の原産地は?
はっきりとわかっていませんが、野生種が見つかったカスピ海の近くや北アフリカが有力です。歴史上では、古代エジプトやギリシャで栽培されていた記録が残っており、人間とは4000年にもなる付き合いということになります。
日本に伝わったのは、奈良時代にシルクロードを経由して中国から来たという説がありますが、定かではありません。実際の記録としては、江戸時代の辞書『多識篇』に蚕豆(ソラマメ)の名前で登場するのが最初なのだそうです。