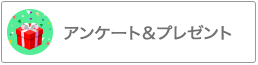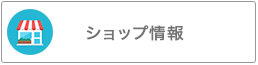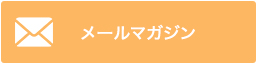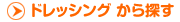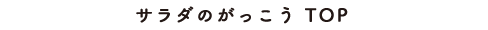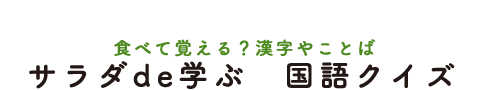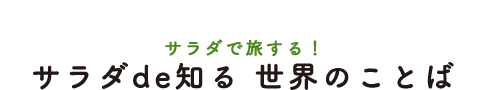日本史クイズ

奈良時代に、
和歌に美味しい食べ方がよまれた野菜とは?
ヒントは、元気が出るけど、
生を食べると匂いが強烈…
答えはイラストをクリック!

日本最古の和歌集『万葉集』に載っています!
答えは、にんにく。昔、にんにくを蒜(ひる)と呼んでいたそうで、長意吉麻呂(ながのおきまろ) の和歌「醤酢に 蒜搗きかてて 鯛願ふ 我れにな見えそ、水葱の羹」
これを現代語にすると、「醤油と酢につぶしたにんにくを入れて、鯛の刺身を食べたいなあ。(味気ない)ミズアオイの吸い物は出さないでね」 ということになるのだそうです。
二杯酢におろしにんにくを添えて、鯛の刺身をいただく…なんて美味しそう!きっと、グルメな歌人だったのでしょうね!
時には愛されたり、嫌われたり…
古くから、にんにくは薬として栽培され、重宝されてきました。しかし、口にした後は、匂いがするので人に会えない…という話が、紫式部の『源氏物語』 に書かれています。また、にんにくに滋養強壮があることから気が荒くなるので、修行している僧侶たちには良くないと、746年にんにく禁止令が出たこともあったそうです。
では、歴史クイズ。にんにくの首飾りをしていたのは誰?
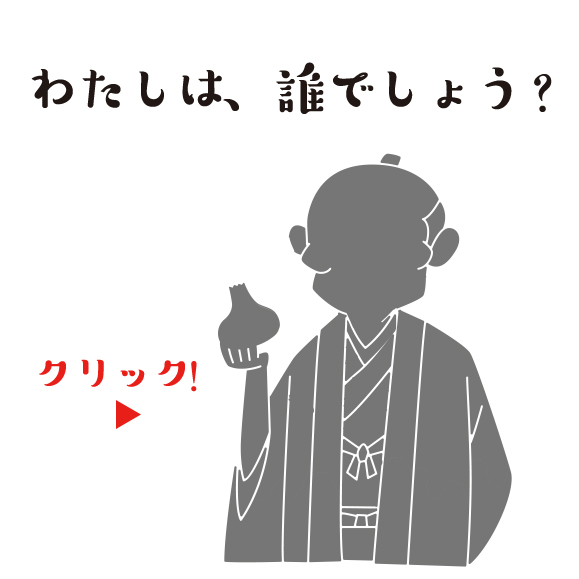
それは、豊臣秀吉!秀吉は若い頃、にんにくを数珠のようにつなぎあわせて首から下げ、それをかじりながら戦っていたとか。にんにくでパワーがでることを知っていたのですね。天下をとった後も、秀吉は戦の前に、兵士ににんにくを与えて力をつけさせていたそうです。
この人もにんにく大好き!
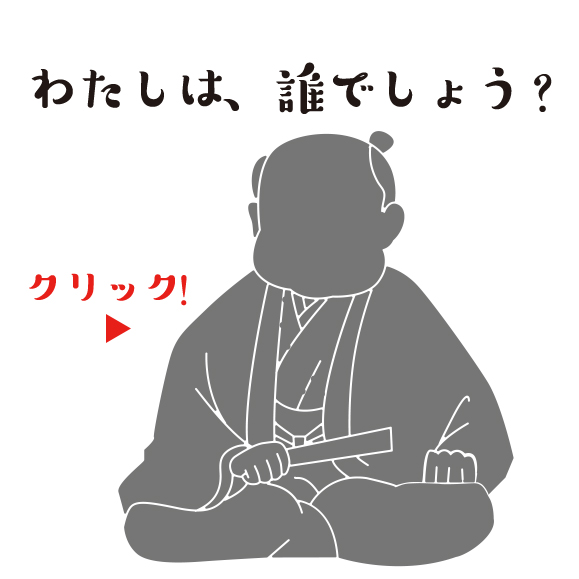
徳川家康も、にんにくをよく食べていたようです。自分で薬草を調合して、自家製サプリメントを服用していた家康ですから、にんにくが健康の秘訣であることを知っていたのでしょうね。大好物の鯛の天ぷらにも、すりおろしたにんにくをたっぷりつけて食べていたそうです。
江戸の庶民にも人気!
元禄の頃、武士の間では口臭が無礼にあたるとして、にんにくを禁じていましたが、庶民は病気や厳しい労働を支える食材として食べていたようです。江戸時代のレシピブック 『料理物語』では、にんにく料理に「汁、さしみ、なます、みそ、すいくち」が挙げられています。江戸の庶民は、にんにく料理で元気いっぱい!になったのでしょうね。